BLOG
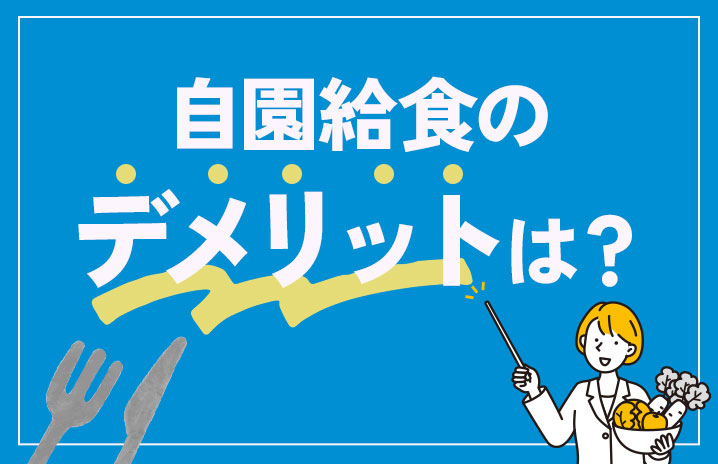
自園給食のデメリットは?給食を委託するメリットデメリットについても解説!
自園給食では、園の方針に沿った柔軟な給食運営を目指せる一方で、採用する栄養士の技量が問われたり、求めるレベルに達するまでには膨大な時間やコストがかかったりといった課題もあります。
委託給食では、これらの課題を一手に引き受け、時間や労力を削減し、園の方針に沿った給食運営が少ない労力で実現可能です。
この記事では、自園給食(直営給食)のメリット・デメリットから、自園給食の強みや委託給食を検討すべきポイントについて解説します。自園給食と委託給食の特徴をしっかり把握し、自園に合った給食運営を目指しましょう。
自園給食のデメリットは?

自園給食(直営給食)では、委託給食と比較して給食運営の自由度が高く、イベントなどに合わせた給食を臨機応変に対応できるのが特徴です。
しかしその一方で、調理員や栄養士を直接雇用するためのコストがかかったり、衛生管理や食の安全確保、料理の質などの給食運営にまつわる技術の成熟に時間がかかってしまう点では、委託給食の方が安定した給食運営を実現できるでしょう。
ここからは、自園給食の主なデメリットと、委託給食との比較について解説します。
1.採用・管理コストがかかる
自園給食の場合、栄養士や調理師など、給食従事者の採用や労務管理を保育園自体でおこなう必要があります。
募集には、広告費や採用時の面接等も必要で、採用までに時間と手間がかかることも把握しておきましょう。さらに、採用後は人件費や社会保険などの福利厚生費、長期採用の場合の昇給や賞与も考慮しなければならず、保育士の雇用と同程度の待遇が求められます。
一方で、委託給食の場合は、給食従事者が保育園の直接雇用ではないため、人材管理のコスト削減が見込まれます。給食従事者の待遇は委託会社の管理となるため、保育園側は契約内容に沿った人件費のみの支払いで済み、保育園自体の運営費の安定も図れるでしょう。
自園給食では、給食従事者の採用・管理コストをあらかじめ把握しておくと安心です。
2.教育リソース・コストがかかる
自園給食では、給食従事者の育成や技術の定着にも時間や労力がかかります。
新規開園ともなれば、給食運営について知識や技術を持ったスタッフの採用が必須となるでしょう。
また、給食運営は各自治体による栄養管理や衛生管理の基準に基づく運営が求められます。研修会などにも積極的に参加し、移り変わる法律や衛生管理基準についても最新の情報を理解し、給食に反映させられる教育体制の整備も必要となるでしょう。
委託給食では、専門知識を持った栄養士の配置や調理員の採用、教育などを委託会社で管理・運営してくれます。保育園側は先ほどと同じく、契約に沿った支払いのみで、給食従事者の育成や技術の定着に対する負担を抱えずに済むのも大きな違いです。
3.園内での調理員の在中が必須となる
自園給食で給食従事者を直接雇用した場合、運営に必要な人数の確保が課題となります。
給食従事者の勤務日数や、急な休みに対応できる人数の雇用を自園でおこなうには、それなりのコストがかかるでしょう。
たとえば、100食作るために3人体制で調理をおこなう場合、一人が月に休む回数、休みが重複した場合の補充、急な休みの対応などを考慮すると、5人程度の雇用が必要です。
さらには、常勤・非常勤など、一人ひとり雇用形態もさまざまなため、勤怠管理も複雑になります。
一方で、こちらも委託給食では、保育園側は契約内容に沿った人件費の支払のみで、委託会社側が人員確保を請け負ってくれます。複雑な勤怠管理が軽減され、経理部門の負担も軽くなるでしょう。
なお、富士産業では調理員が急な休みとなった場合、近隣の受託先に配属しているスタッフが応援要請で対応することもあります。
4.園内に調理室があることによる衛生管理・食の安全の確保にもリソースが必要
自園給食では、調理室の衛生管理や食の安全管理についても専門的な知識を持って対応しなければなりません。
保育園給食の衛生管理は、各自治体の基準に基づいた対応が必要で、現場の衛生管理とそれを記録した関係書類の整備には、一定の知識や技量を要します。前述と同様に、専門的な知識を持ったスタッフの採用や教育が課題となるでしょう。
委託給食では、衛生管理や給食運営にまつわる書類の整備も請け負ってくれます。また、教育体制の整った委託会社を選定すれば、法律や基準の改定にも柔軟で、指導監査にも対応してくれます。
自園給食で衛生管理や食の安全に関する課題を抱えている場合、委託給食へ切り替えることで、保育園の負担も軽くなるでしょう。
5.雇用する栄養士の個の技量が必要となる
自園給食の場合、献立の栄養管理や衛生管理、食育やアレルギー対応といった専門分野は栄養士の力量に大きく左右されます。
会社独自で栄養士の教育体制を整えている委託会社も多く、安心して業務を任せられるでしょう。
自園給食では、栄養士の技量を重視した採用が給食運営成功のカギといえます。
自園給食のメリット

自園給食(直営給食)には、人材管理や運営管理にまつわる課題も多くありますが、自由度が高いことが最大のメリットでしょう。
園児の体調に合わせたメニューへの対応や、地産地消・食育へのこだわりなどの反映させやすさは、自園給食ならではです。
ここからは、自園給食のメリットについて詳しくみていきます。
園のコンセプトに合わせた給食が実現できる
自園給食の最大の強みは、園のコンセプトや方針に沿った給食提供がかなうことです。
もちろん、園が雇用した調理員には、給食業務に関する知識の教育以外にも、より保育の観点で給食運営ができるでしょう。
たとえば、先月まで手づかみで食べていた子どもが、指先で細いひものおもちゃで遊べるようになったら、離乳食もつまみやすい細長い形態に移行するタイミングです。
このように、子どもの成長具合と食事をリンクさせることで、その子の発達に合った食事提供ができます。子どもの成長や発達を保育者と同じ目線で見守ることで、園の方針や給食のあり方に理解を示す調理従事者の教育ができるでしょう。
コストや時間は必要ですが、自園給食による調理員の教育で、委託業者では対応しにくい、園の給食運営の土台を作り上げられます。
園児の体調に合わせたメニューなどを臨機応変に対応可能
自園給食では、園児一人ひとりの体調やアレルギー、発達段階に応じて柔軟な対応ができます。
もちろん、委託給食でも同じような対応は可能です。しかし、委託会社との契約内容によっては対応に時間がかかる場合があります。また、園の方針といった微妙なニュアンスは、自園給食の方がよりきめ細やかな対応ができるでしょう。
さらに、離乳食やアレルギー食の対応では、給食担当者が直接保護者に聞き取りが必要な場面も想定されます。そのような場合に、「委託の栄養士さん」より「自園の栄養士さん」の方が、保護者もより安心して要望を伝えやすくなり、園のイメージアップにも貢献できるでしょう。
園の方針や園児一人ひとりの細やかな対応は、自園給食の強みです。
食材の調達〜調理・配膳の管理が自園でできる
自園給食では、食材の調達から調理、配膳までを自園が管理するため、地産地消や食材へのこだわりを取り入れやすいのがメリットです。
納品業者の選定に手間はかかりますが、産地や価格をよく吟味できれば、安全な食材を安心して園児に提供できるでしょう。
調理や配膳など、子どもの口に入るまでを自園が責任を持って提供できる点で、保護者への安心感にもつながります。自園の調理員や保育士が、子どもたち一人ひとりをしっかり見て、細やかな対応を心がけることで、園の信頼感もアップさせられるでしょう。
自園給食による給食運営管理は、自園のこだわりを柔軟に反映させ、保護者の安心感や信頼感を高められます。
自園給食を辞めて委託にするとどんなメリットがある?

自園給食(直営給食)から委託給食に切り替えると、コストの削減や保育士の負担軽減、食育やイベントでのより専門性の高いサポートが受けられます。
人員の入れ替わりで給食の質が保てない、給食従事者の教育方法が分からないなどの課題を抱えている保育園は、委託会社に切り替えることでこれらの課題を解決できる可能性があります。
ここからは、委託給食に切り替えた場合の具体的なメリットについて見てみましょう。
採用・教育・管理コストを削減できる
委託給食を導入すれば、採用や教育、福利厚生に関するコストを削減し、給食運営費自体の安定化が図れます。
自園給食を実施する地方の園では、専門職員の確保が難しく、採用活動に苦戦することも少なくはありません。職員の急な欠員や産休・育休にも対応しなければならず、人員確保の手間やコストの負担は大きくなるでしょう。
委託給食では、基本的に委託会社が人材の管理を請け負ってくれます。園側は人材に関する費用や労務管理の手間を削減することで、本来の保育業務に集中できるようになり、自園の保育サービスをより良くすることにもつながるでしょう。
人材管理に課題を感じる場合、委託給食の導入で労務負担を解消し、給食運営の安定化を実現できます。
富士産業では、年間での計画的な研修内容をきめ、スタッフの衛生教育の取り組みを徹底しています。給食運営で重要な衛生管理なども安心して依頼が可能です。
保育士の負担を軽減できる
委託給食の導入で、離乳食やアレルギー食対応をする保育士の負担を軽減できます。
委託会社から配置される経験豊富な栄養士や調理員が、子どもの年齢や発達、アレルギーに対応した献立作成や調理をおこなったり、保育士とともに直接保護者への聞き取りをおこなう場合もあります。
特にアレルギー食の対応では、子どもの発達の知識だけでの対応は難しく、医師が発行するアレルギー食の指示書を読み取り、献立に反映させるスキルが必要です。
保育園給食では、栄養士の配置は義務付けられてはいませんが、専門知識のある栄養士が配置されていることは、保護者の安心にもつながり、園自体の強みにもなるでしょう。
委託給食ならではの専門性を活かすことで、保育士の業務負担も削減できます。
園児に合わせた質の高い食事を提供できる
委託会社に給食を依頼すると、経験豊富な栄養士・調理員が、子どもの年齢や発達段階に合わせた食事の種類や衛生管理に対応し、質の高い給食を提供できます。
栄養士の配置がない保育園の給食では、栄養価計算に対する知識を持ったスタッフがいないために、公立の献立やサイクルメニューで対応していたり、園のイベントや行事食を取り入れられなかったり、献立を制限せざるを得ない園も少なくありません。
委託給食では、委託会社の栄養士が自園に合った方針を理解しつつ、栄養管理から離乳食・アレルギー食対応までを任せることができます。
自園の実態や要望に応じた食事で、バラエティに富んだオリジナルの給食提供を実現できるでしょう。
献立のバリエーションやイベント食への対応にお悩みの場合、委託給食の導入を検討するタイミングです。
専門性を持って「食育」「イベント」などをサポートしてもらえる
委託会社では、依頼があれば食育活動のサポートも可能です。
栄養士が3歳以上児を対象にクラスで授業をおこなったり、手作りおやつ体験のサポート、担任がおこなう食育活動の補助など、保育現場のニーズに合わせた食育活動を実行してくれます。
委託会社には、食育に関する豊富な経験とノウハウが蓄積されている会社がほとんどです。給食のプロが園の食育活動に寄り添い、きめ細やかなサポートが受けられるでしょう。加えて、栄養バランスを考慮しながら、季節や行事に合わせたメニュー内容を提供できます。七夕やクリスマス、節分などはもちろん、遠足のお弁当など園行事にも合わせた献立を展開してくれるでしょう。
委託給食で、食育としての意義もしっかり果たしつつ、子どもたちの食の楽しみを広げてくれる給食運営ができます。
自園給食から委託会社切り替えの際の注意点

自園給食(直営給食)から委託給食への切り替えには、信頼できる委託会社の選定が大切です。
選定の際には、栄養士の個の力量を感じられる会社であるか、自園の方針を理解してくれるかなどに注意しながら選定するとよいでしょう。
ここからは、委託会社の選定で注意すべきポイントをまとめます。
自園の目指す給食運営に寄り添ってくれる会社選びを意識しましょう。
栄養士の力量が感じられる委託会社を選ぶ
自園給食から委託会社へ切り替える際には、栄養士の力量が確認できる委託会社を選ぶことが重要です。
保育園では、離乳食から就学前の児童の食事まで、年齢によって量や調理形態の異なる幅広い食事に対応しなければなりません。委託会社には、これらの課題に柔軟に対応できる経験豊富な栄養士が在籍しているかを確認しましょう。専門性の高い提案で、保育士も保護者も安心できる給食提供が可能になります。
委託会社独自の経験やノウハウに基づいた、質の高い給食提供も期待できるでしょう。
自園の方針を理解し寄り添いつつ運営計画を立てられる委託会社を選ぶ
自園給食から委託給食へ切り替える際は、園の方針や保育内容を十分理解し、それに寄り添った給食運営を計画・提案できる委託会社を選びましょう。
これまでの自園給食で培ってきた食育の取り組みや、献立のこだわり、食材の選定基準など、大切にしてきたことに対して理解を示し、尊重してくれる会社が理想です。自園の良さを引き継ぎつつ、さらに質の高い給食を提供できるよう、具体的な提案をしてくれる会社を見極めましょう。
また、委託会社の担当者とのコミュニケーションがスムーズに取れるかどうかも重要なポイントです。定期的な打ち合わせや情報共有を通じて、密な連携を図れる会社を選びましょう。
子どもの発達・発育に応じての栄養バランスを考えてくれる委託会社を選ぶ
子どもの年齢や発達段階に合わせた栄養管理や食事の提供ができる会社を選定しましょう。
特に認可保育園の場合、各自治体による栄養摂取基準を満たさなければならず、食事の管理は重要です。摂取基準を満たしながら、園の実態に沿った給食を提供できる会社であるかをしっかり見極めましょう。
また、アレルギーや離乳食などの個別対応が充実しているかもポイントとなります。
園の方針に寄り添いつつも、子どもたちの成長をきちんとサポートできる会社を選びましょう。
自園の方針に合わせて委託会社を選ぶのが大切
今回は、自園給食(直営給食)のメリット・デメリットを押さえ、自園給食の強みや委託給食を検討すべきポイントについて解説しました。
自園給食で園の方針に沿った形の給食提供をおこなうには、時間をかけた教育とノウハウの蓄積が大切です。一方で委託給食を導入すれば、専門の知識やノウハウをそのまま活用でき、園独自の給食運営を、時間をかけずかなえられるでしょう。
富士産業では、そんな保育園に寄り添った最適な提案のできる栄養士や調理員が多く在籍しています。
子どもたちが楽しめる豊富なバリエーションの食事を提供可能です。
- 定番メニュー
- 季節のメニュー
- 行事メニュー
- 地域の特産メニュー
など、食を通じて楽しむことと学ぶことの両立を目指しています。
富士産業では、部分委託や全面委託、労務委託など、園のニーズや状況に合わせて柔軟にサポートすることが可能です。
自園の方針や要望を丁寧にヒアリングし、子どもたちにとってより良い給食運営を実現しましょう。